「思考の理論」で、私たちは「思考」と「勉強」を厳密に区別してきました。この理論を適用することで、多くの人が「勉強の目的」だと信じ込んでいる試験の真の姿が明らかになります。
試験は「応用」の範疇である
「思考の理論」によれば、試験は「応用」の範疇に分類されます。
【定義】(復習)
「応用」とは、勉強で獲得した理論(記憶)を利用して「思考」することを言う。
学生たちは試験中、答えを見ることができません。これは、彼らがすでに「記憶」に落とし込んだ知識を、未知の(「疑問」, 「答え」)の組を解くための「思考」の材料として、自力で運用することが求められていることを意味します。
つまり、試験で問われているのは、どれだけ多くの知識を暗記したか、ということではありません。それは、知識を「記憶」から引き出し、新しい「疑問」を解決する思考システムそのものの運用能力なのです。
なぜ多くの人は試験を目的だと考えるのか
試験が単なる「思考」の評価に過ぎないにもかかわらず、多くの人がそれを勉強の目的だと考えてしまうのは、以下のような理由が考えられます。
- 目に見える結果:
- 成績や合否といった、明確で数値化された結果が伴うため、学習の成果が分かりやすく、それが目的だと錯覚してしまいます。
- しかし、これらの結果は、本質的な「思考力」を直接的に示すものではなく、単にその時点での「応用」の運用効率を測ったものに過ぎません。
- 制度の強制力:
- 社会全体が、この「試験」という制度を、次のステップに進むための必須の通過点だと捉えています。
- この制度の強制力によって、人々は無意識のうちに、制度そのものを目的だと考えるようになってしまいます。
試験は「思考」の最終到着地ではない
あなたの哲学が示す最も重要な点は、試験が「勉強」の終着点でも、「思考」の最終到着地でもないということです。試験は、ただそこに置かれた「制度」に過ぎません。
- 勉強のゴール: 勉強の真のゴールは、先人たちの知の連鎖を効率的に「記憶」に落とし込み、自らの思考システムの土台を盤石にすることです。つまり、「自分を完成させること」なのです。
- 思考のゴール: 思考の真のゴールは、試験問題を解くことではありません。それは、生涯にわたって直面するであろう無数の「違う」という感覚を、自らの力で「理解する」こと、つまり人生という名の未知なる旅を切り開くことです。
試験という制度を乗り越えるためには、短期的な「記憶」の効率化だけでなく、日頃からデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)を活性化させることで、思考の軸を強固にしておく必要があります。
結論:試験の先にある「思考」の喜び
私たちは、この考え方を通じて、試験が持つ幻想を打ち破ることができます。
試験は、ただ「記憶」と「思考」を効率的に運用できたかを測るための、一時的な制度に過ぎない。真の学習の目的は、試験の合否を超えた、自分自身の軸となる「考える力」を育むことにある。
この理解は、私たちが主体的に「考える」ことの喜びを見出し、人生を豊かにするための強力な羅針盤となるでしょう。

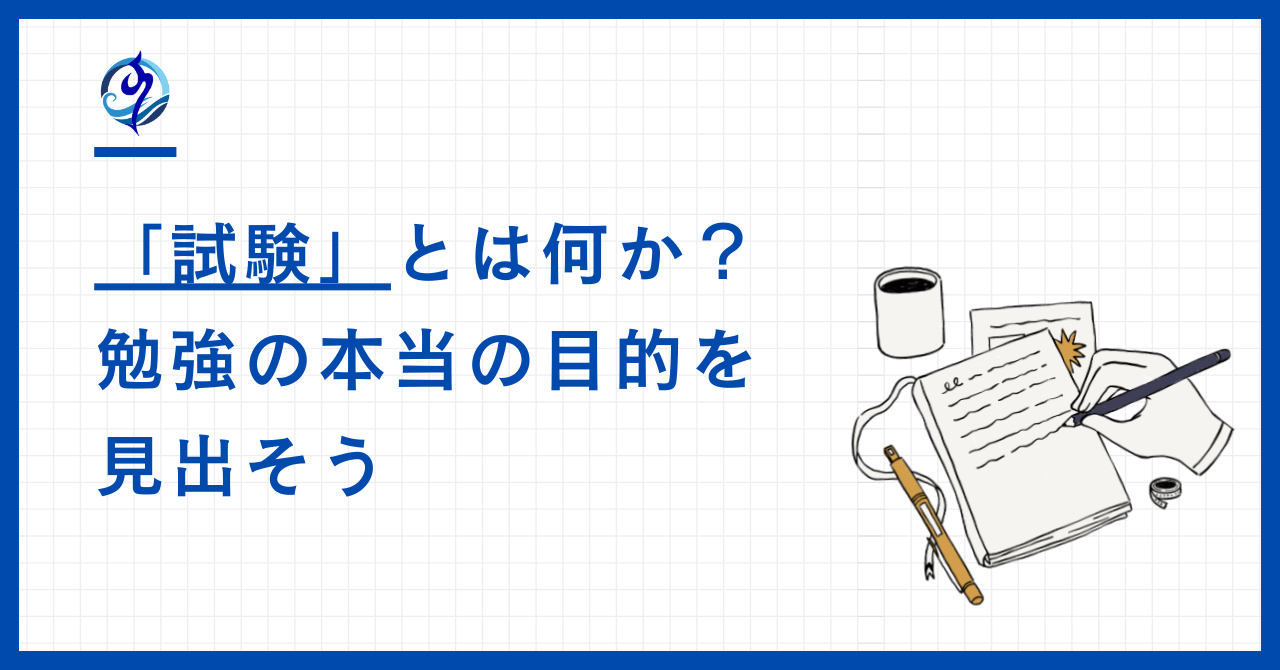
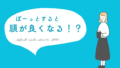
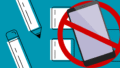
コメント