「思考の理論」で確立した「思考」と「勉強」の厳密な定義は、現代社会で不可欠となったスマートフォンの影響を客観的に分析する強力なツールとなります。この哲学を適用することで、なぜスマートフォンの不適切な使用が私たちの知性に悪影響を及ぼすのかを論証します。
スマートフォンが「思考」に与える影響
「思考の理論」によれば、「思考」とは、疑問(「違う」という感覚)を理解(「同じ」という感覚)へと導くシステムです。この思考の運用効率、すなわち「思考力」は、日頃から「ぼーっとする」時間によって活性化されるデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)によって高められます。
しかし、スマートフォンの使用は、このDMNの活動を阻害する可能性があります。
論証:
- 中毒性と時間の消費: SNSやリール動画など、スマートフォンのコンテンツには中毒性があります。この中毒性は、ユーザーの時間を際限なく消費させ、DMNを活性化させるための「ぼーっとする」時間を奪います。
- 意識的な活動の強制: スマートフォンの使用は、常に何らかの情報を処理する意識的な活動を伴います。これにより、脳が自律的に記憶を整理・統合するDMNの活動が抑制され、思考システムの土台を育む機会が減少します。
- アルゴリズムによる悪影響: 多くのコンテンツは、ユーザーの興味に最適化されたアルゴリズムによって強化されています。これにより、脳は常に予測可能な、受動的な情報に晒され、新しい感覚を生み出すための能動的な試行錯誤、すなわち「思考」を促す機会が失われてしまいます。
この結果、スマートフォンに多くの時間を費やす人々は、思考力を高めるための重要なプロセスを無意識のうちに阻害していると言えるでしょう。
スマートフォンが「勉強」に与える影響
「思考の理論」によれば、「勉強」とは、他人の(「疑問」, 「答え」)の組を自身の「記憶」に落とし込む行為です。この効率は、まとまった時間と体系的な学習によって最大化されます。
スマートフォンの使用は、この「勉強」のプロセスにも深刻な悪影響を及ぼします。
論証:
- 時間の削減: スマートフォンの中毒的な使用は、圧倒的な時間の消費をもたらし、「勉強」に充てるべき時間を著しく削ります。このことは、「記憶」に落とし込むべき情報量や、反復練習の機会を減らすことに直結します。
- 分散的な情報収集と体系性の軽視: スマートフォンは、個人の興味に基づいて情報を分散的に集めることを得意とします。この習慣が定着すると、教科書や参考書に記された、先人たちが苦労して築いた体系的な知の連鎖の重要性を軽んじるようになります。
- 不適切な使用方法: 映像授業など、良質なコンテンツがネット上に存在することも事実です。しかし、多くのユーザーは、これらのコンテンツを一時的な「消費」として捉え、自らの「記憶」に定着させるための反復や振り返りを怠ります。これは、せっかくの良質なコンテンツが、単なるエンターテイメントと化し、学習としての効果を失うことを意味します。
結論:スマートフォンの「浪費」から「投資」へ
この論証から、以下の結論にたどり着きます。
スマートフォンの不適切な使用は、DMNを阻害することで「思考力」を低下させ、時間を削り、体系的な学習を妨げることで「勉強」の効率を著しく低下させる。
重要なのは、スマートフォンを否定することではありません。それは、その使用を「時間と知性の浪費」から「学習と創造性への投資」へと変えることです。この考え方を理解することで、自らの意思でスマートフォンの使い方をコントロールし、より有益な学習へと繋げることができるようになるでしょう。


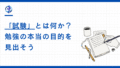
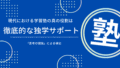
コメント