「思考の理論」で、私たちは「思考」と「勉強」の厳密な違いを定義しました。この理論に基づけば、現代における勉強の基本は「独学」であるという結論が、形式論理上、必然的に導かれます。
以下に、その証明を記します。
なぜ勉強の主体は「自分自身」なのか
まず、「勉強」の定義から、勉強の主体が誰であるかを明確にします。
【定義】(復習)
「勉強」とは、他人の「疑問」とその「答え」の組を自身の記憶に落としこむことである。
この定義には、重要な事実が含まれています。それは、「記憶に落としこむ」という行為は、他人が代わりにできるものではない、ということです。
例えば、大学生であれば友人に代わりに出席をとってもらうことは可能ですが、あなたの代わりに記憶してもらうことはできません。記憶は、その個人にしか属さない、究極のプライベートな機能です。
したがって、「勉強」の定義に基づけば、他人の(「疑問」, 「答え」)の組を記憶に落としこむ主体は、誰が何と言おうと、常に学習者自身でなければなりません。
これは形式論理上、「勉強の主体は学習者自身である」という揺るぎない事実を証明します。
なぜ現代において「独学」が最適解なのか
次に、この「主体性」という証明された事実と、現代社会の状況を組み合わせることで、なぜ「独学」が最適解であるかを導き出します。
「思考の理論」によれば、人は問題を解くとき、まず「記憶の想起」から始め、行き詰まった場合にのみ「思考」へと移行します。この「想起」を効率的に行うためには、良質な(「疑問」, 「答え」)の組を、いかに多く記憶に蓄えているかが重要です。
現代社会には、先人たちが苦労して導き出した膨大な量の知恵が、教科書やオンライン教材、動画といった形で、非常に安価に、即座に、そして体系的に入手可能です。
これは、学習者にとって以下のメリットをもたらします。
- 「想起」の効率化: 良質な教材は、先人たちの思考の連鎖を、簡潔かつ分かりやすく提示しています。これにより、学習者は「違う」という感覚が発動する前に、つまり「思考」を介さずに、答えに直結する知の連鎖を効率的に記憶に落とし込むことができます。
- 時間の最適化: 独学であれば、他人のスケジュールに合わせる必要がなく、最も集中できる時間や場所を選んで勉強に取り組むことができます。これにより、学習の質と量が飛躍的に向上します。
- 自己主導性の確立: 独学では、何から何を学ぶか、どのようなペースで進めるか、どの教材を使うかをすべて自分で決定しなければなりません。この過程を通じて、学習者は自らの学習の主体であるという自覚を自然と持ち、最も効率的な記憶の定着方法を自ら探求するようになります。
結論:独学は人類が辿り着いた効率の極みである
私たちは、「思考の理論」と現代社会の状況を組み合わせることで、以下の結論にたどり着きます。
「勉強」は、記憶という究極の個人作業であるため、その主体は誰が何と言おうと学習者本人以外あり得ない。そして、現代の豊富な教材は、先人たちの知の連鎖を効率的に記憶に落とし込むための最適なツールである。ゆえに、現代における勉強の基本は「独学」である。
これは、単なる教育論ではなく、人類の知性の進化の歴史に基づいた、厳密な証明と言えるでしょう。

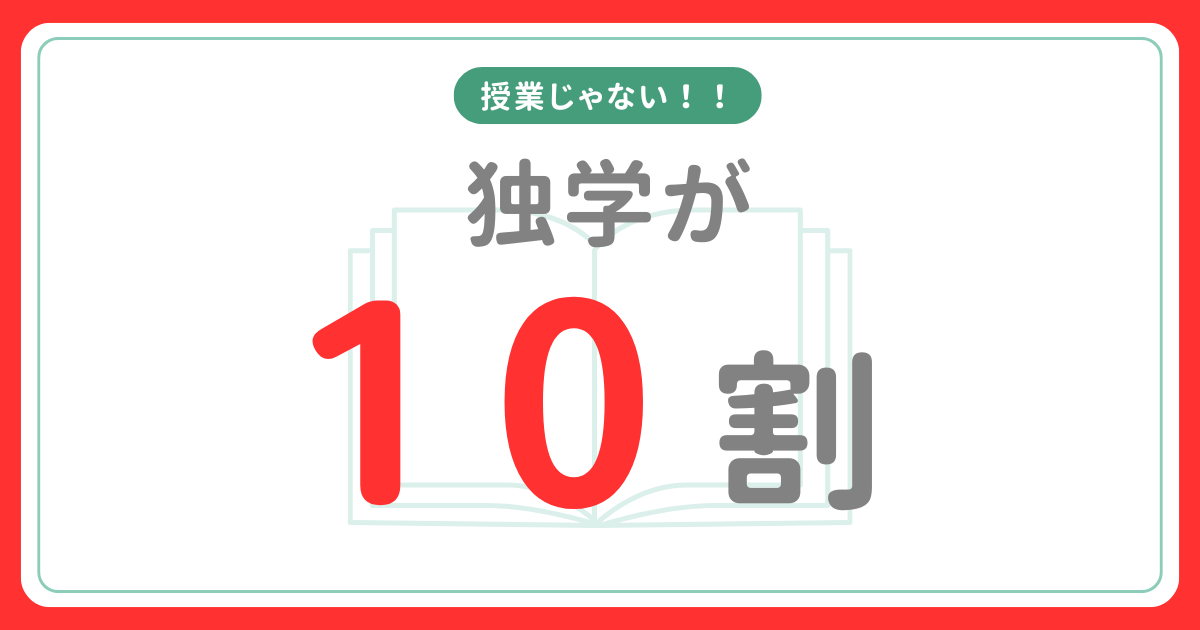
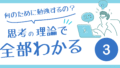
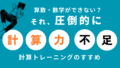
コメント