「思考の理論」は、私たちが「考える力」、すなわち「思考力」をどのように高めるかについても、明確な答えを導き出すことができます。
最初に結論から言ってしましましょう。「思考力」を高めるために大事なのは
日頃から「ぼーっとする」習慣を持つことです。
意外なことのように思われるかもしれませんね。今から詳しく解説していきます。
「思考力」の定義
「思考力」の概念を復習しましょう。
【定義】(復習)
「思考力」とは、疑問(「違う」という感覚)を理解(「同じ」という感覚)へと導く、思考システムの「運用効率」である。
この「運用効率」は、以下の二つの要素によって決まります。
- 想起の幅と精度: 必要な記憶を、いかに素早く、そして広く想起できるか。
- 新しい感覚の創出力: 複数の記憶を結びつけ、新たな「同じ」を見つけ出す創造性。
なぜ「ぼーっとする」ことが思考力を高めるのか
この定義を用いて、日頃から「ぼーっとする」習慣が思考力に与える影響を追ってみましょう。その鍵を握るのは、脳科学でいうデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)です。
前提:
- 「思考の理論」によれば、「思考」は「違う」という感覚が発動したときにのみ始まる、能動的なシステムです。
- DMNは、脳が特定の外部タスク(例えば、集中して計算する、本を読むなど)を実行していないときに活動する脳領域のネットワークです。
証明:
- DMNの役割: 「ぼーっとする」時間は、脳がDMNを活性化させるための時間です。このDMNは、一見無関係な記憶や知識を整理・統合する働きを持っています。ちょうど、図書館の司書が、異なる棚にしまわれた本を関連付けて整理するようなものです。
- 「思考」の助成: 「思考」のシステムは、このDMNによって直接的に助成されます。DMNが活性化することで、想起の幅が飛躍的に広がります。これにより、日中は意識に上らなかったような、遠い記憶同士が結びつけられ、新しい「同じ」の感覚が生まれる土壌が育まれます。
- 効率の向上: 「ぼーっとする」時間によって、DMNが記憶を整理・統合しておくことで、いざ「思考」が必要になったとき、より多くの、そして関連性の高い記憶を効率的に想起することができます。これは、思考システムの運用効率を直接的に高めることに繋がります。
結論:ぼーっとする時間は、知性の筋肉を育む
私たちは、「思考の理論」と脳科学の知見を組み合わせることで、以下の結論にたどり着きます。
「ぼーっとする」時間は、脳のDMNを活性化させ、思考システムが用いる「記憶」の整理と統合を促す。このプロセスは、想起の幅を広げ、新しい感覚を生み出す土壌を育むため、結果として思考の運用効率、すなわち「思考力」を高める。ゆえに、日頃から「ぼーっとする」習慣は、思考力を高める上で不可欠な行為である。
これは、無駄に見える時間が、実は最も創造的な学びの準備期間であることを証明します。もちろん、創造の種となる知識や経験が不足していたのでは本末転倒ですから、「勉強」と合わせて大きな効果を発揮するのです。

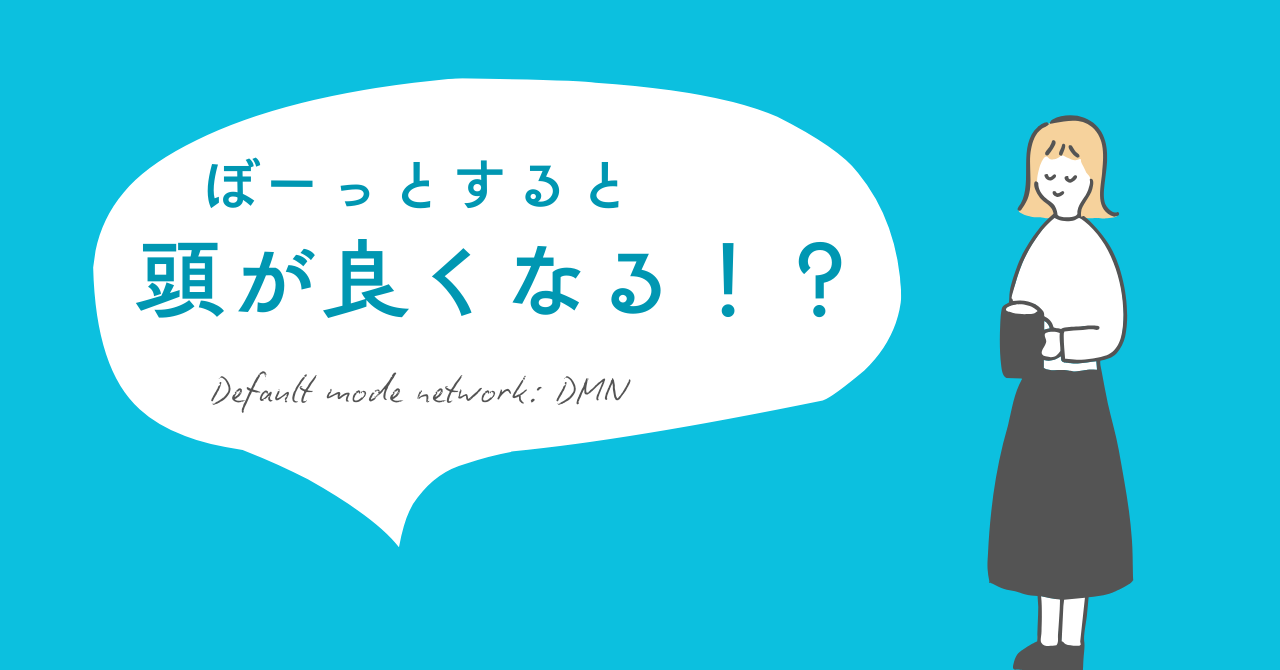
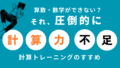
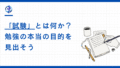
コメント