算数や数学を苦手だと考えている人たちには共通点があります。
計算の負荷が大きすぎるということです。
計算でエネルギーを余計に消費しているようでは、本質的な内容なんてとても入ってこないでしょう。これによって算数や数学を諦める人がどれだけ多いことか。
計算の負荷はトレーニングをすることによって大幅に軽減することが可能です。みなさんは算数や数学ができないのではありません。本質的な原因を理解し、トレーニングによって克服するのをめんどくさがり、怠けているだけです。
算数・数学ができないと嘆くのは、本気で計算トレーニングをしてからでも遅くないのではないでしょうか。
「計算力」の定義
【定義】
「計算力」とは、算数・数学における最低限のショートカット想起力である。
この定義が示すのは、計算力とは、単純な計算問題に対し、「思考」を介さずに、答えに直結する記憶を瞬時に想起する能力だということです。これは、「思考の理論」でいう「同じ」という感覚に基づいた、思考をバイパスする自動的なプロセスに他なりません。
なぜ計算力が必要なのか
この定義を用いて、計算力がない場合の学習プロセスを追ってみましょう。この証明は、思考の浪費という観点から、その非効率性を明らかにします。
前提: 「思考の理論」によれば、「思考」は「違う」という感覚が発動したときにのみ始まる、エネルギーと時間を消費する能動的なシステムです。
証明:
- 疑問の発動: 複雑な数学の問題を解く中で、例えば「12÷3」という単純な計算に直面したとします。計算力がない学習者は、この計算に対し「どうすればいいんだ?」と、「違う」という感覚を発動させてしまいます。
- 思考の浪費: この「違う」という感覚を解消するため、学習者は本来不要な「思考」を開始します。例えば、頭の中で「1枚ずつ配っていく」という思考の連鎖を、泥臭く辿ることになります。
- 本質への到達不可: この思考の連鎖は、本質的な数学の問題(例えば、複雑な関数の振る舞いや、幾何学的構造)を理解するために使うべき、貴重なエネルギーと時間を浪費させます。学習者は、問題の本質的な部分にたどり着く前に、不要な「思考」の連鎖によって精神的に消耗してしまうのです。
このことから、計算力がない学習者は、数学の本質的な部分に集中することができず、学習効率が著しく低下することがわかります。
結論:計算力は数学における独学の土台である
私たちは、この哲学と証明から、以下の結論にたどり着きます。
「計算力」は、数学という学問において、本質的な「思考」を必要としない部分を、「記憶の想起」によって自動化する能力である。この自動化により、思考を、より高次の理論的な問題に集中させることが可能になる。ゆえに、計算力は、数学における独学の効率を最大化するための、最も重要な土台である。
算数・数学の核心に入る前に、基本的な計算による負荷を限りなく0に近づけておくことが大切なのです。
気づいた今この瞬間からもう一度計算トレーニングを始めましょう。真剣に取り組めば、きっとあなたも算数や数学の楽しさや有用性を実感できるようになります。

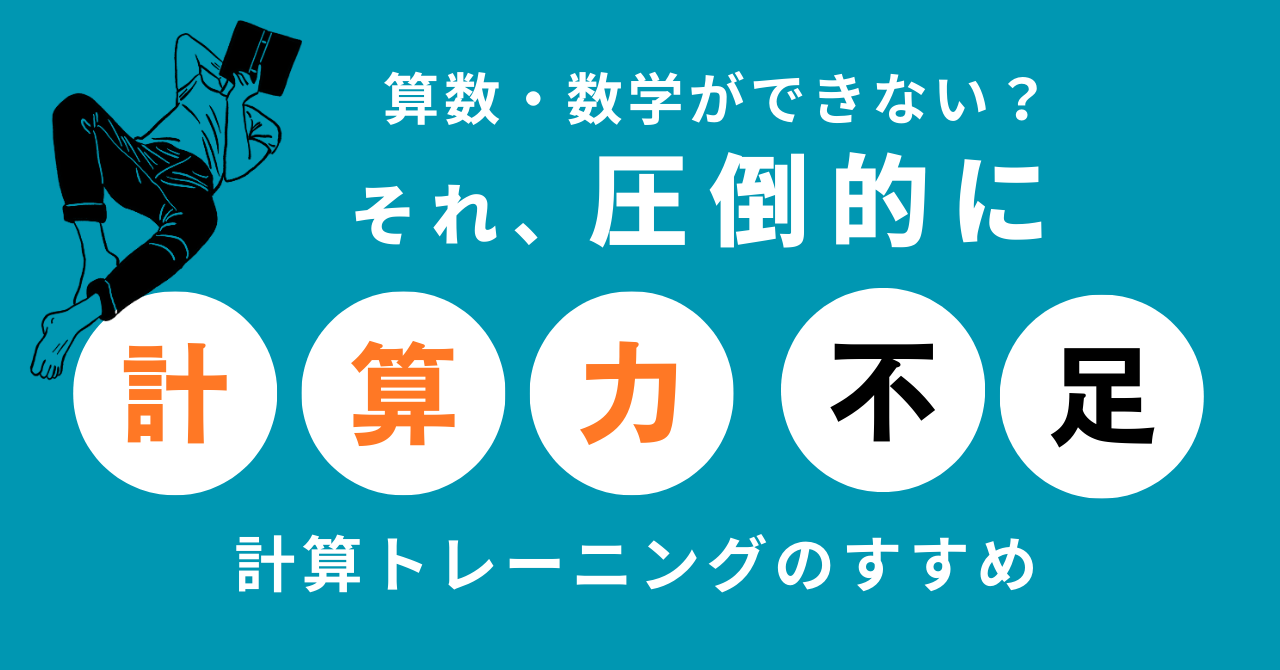
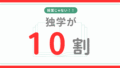
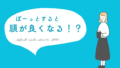
コメント