これまでの記事で、「思考」が「違う」から「同じ」へ向かうシステムであることを理解しました。
では、私たちがこれまで「勉強」と呼んできた行為は、一体何だったのでしょうか? そして、それを「思考」とどう使い分ければいいのでしょうか?
「勉強」の本当の役割
多くの人は「勉強=思考」だと考えています。しかし、それは大きな誤解です。
「勉強」とは、先人たちが苦労して見つけた「答え」を、効率的に自分の「記憶」に落とし込む行為です。
これは、新しい感覚を生み出す「思考」とは全く異なります。
例えば、歴史の年号や、数学の公式を覚える行為。
これは、すでに確立された知識を、自分の頭の中にインストールする作業です。この作業は、どれだけ苦労して覚えようとしても、本質的には「思考」の連鎖は発生しません。ひたすら「記憶」を定着させる作業なのです。
「思考」の本当の役割
一方、「思考」は、記憶という土台を使って、「疑問」に立ち向かうときに発動します。
- 数学の公式を記憶するのは「勉強」。その公式を使って、未知の問題を解くのが「思考」。
- 歴史上の年号や出来事を覚えるのは「勉強」。なぜその出来事が起こり、どう世界に影響を与えたかを考察するのが「思考」。
私たちが「頭を使っている」と感じるのは、この「思考」の連鎖が動いているときなのです。
なぜ、私たちは混同してしまうのか?
私たちが「勉強」と「思考」を混同してしまう最大の原因は、学校教育にあります。
学校では、「覚えたことをテストで書く」というアウトプットが求められます。しかし、これは「覚えたかどうか」を確かめているに過ぎず、「思考」の成果を測っているわけではありません。
結果として、私たちは「たくさん暗記すること=頭が良い」という誤った認識を持ってしまいます。そして、「なぜ勉強するのか?」という本質的な問いへの答えを見つけられず、学習を苦痛に感じてしまうのです。
まとめ:学習の真のプロセス
真の学習プロセスは、次の2段階で成り立っています。
- 「勉強」で土台を作る: 独学によって、効率的に知識を「記憶」に定着させる。
- 「思考」で道を拓く: 記憶した知識という土台を使って、自分の頭で未知の問いに「答え」を見つけ出す。
テラルゴは、あなたがこの真のプロセスを理解し、主体的に実践できるよう、全力でサポートします。
次回の最終回では、この哲学すべてを統合し、テラルゴがなぜ、あなたにとって最適な学びの場なのかを詳しく説明します。

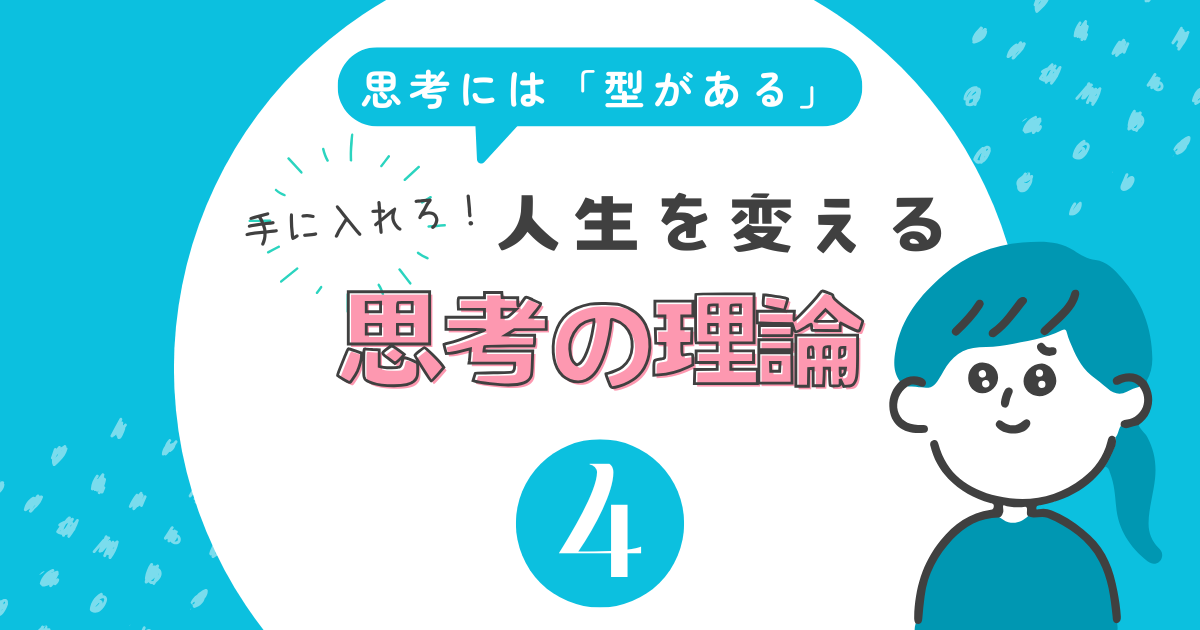
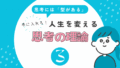
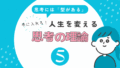
コメント