これまでの議論で、私たちは「思考」と「勉強」をはっきりと区別してきました。この理論の最終段階として、これらの要素がどのように組み合わさり、学習を次のレベルへと引き上げるのかを解き明かします。
「応用」の定義
「応用」を以下のように厳密に定義します。
【定義】
「応用」とは、勉強で獲得した理論(記憶)を利用して「思考」することをいう。
これは、「応用」が「思考」の一種であることを示しています。つまり、短期間で集中的に勉強で獲得した記憶を、自身の「疑問」を「理解する」べく、試行錯誤のために想起することです。
応用学習のプロセス
この定義から、効果的な応用学習のプロセスは以下のように展開されます。
- 「違う」の認識:未知の、複雑な問題に直面したとき、「どう解けばいいんだ?」という「違う」の感覚が発動します。この感覚こそが、「応用」の出発点であり、「思考」の開始信号です。
- 記憶の想起:過去に「勉強」で獲得した(疑問, 答え)の組を、自らの記憶から手探りで想起します。この段階では、どの理論(記憶)がこの問題に「同じ」であるとみなせるかを試行錯誤します。
- 「思考」の構築:複数の記憶を組み合わせて、新しい感覚を生み出す「思考」の連鎖を構築します。このプロセスは、まるで点と点(個々の記憶)を線で結びつけ、新しい図形(問題の解決策)を描くようなものです。
例:数学の応用問題
- 「違う」:未知の応用問題を見て、「この問題、解いたことないぞ!」と直感的に感じます。
- 想起:「待てよ、この問題のこの部分は、あの三角関数の公式と同じだ」「この部分は、あの微分の概念と同じだ」と、バラバラの記憶を想起します。
- 「思考」:これらの想起した記憶を、まるでパズルのピースのように組み合わせ、新しい解放という「思考」の連鎖を構築します。そして、最終的に「とけた!」という「理解」の感覚に達します。
応用学習がもたらすもの
「応用」は、単なる知識の利用ではありません。それは、知識を自分のものにし、新しい「疑問」を解決するための、創造的で能動的なプロセスです。
「勉強」は、他人の知の連鎖を効率的に記憶に落とし込む行為であり、学習の「基礎」を築きます。一方、「応用」は、その基礎を土台に、自らの力で未知の領域を切り開く行為であり、学習の「頂点」を極めるものです。
まとめ
「思考」と「勉強」の概念から、私たちは「応用」の概念の厳密な定義を得ることができました。
- 「応用」とは、「勉強」で獲得した記憶を利用して「思考」することである。
- 「応用」は「思考」の一種である。
- 「応用」は、自らの力で未知の領域を切り開くという、学習の「頂点」を極めるものである。
これにて「思考の理論」の解説は終わりです。
「思考の理論」を利用すれば、数多くのものごとをハッキリと捉え、スッキリと記述することができるようになります。
あなたがこのシンプルな考え方を「軸」として、これから出会う様々な困難を解決することに役立ててくれたのならば、幸いです。

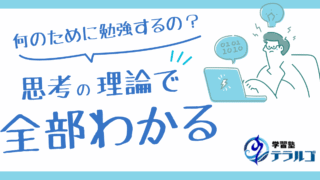
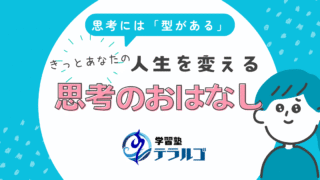
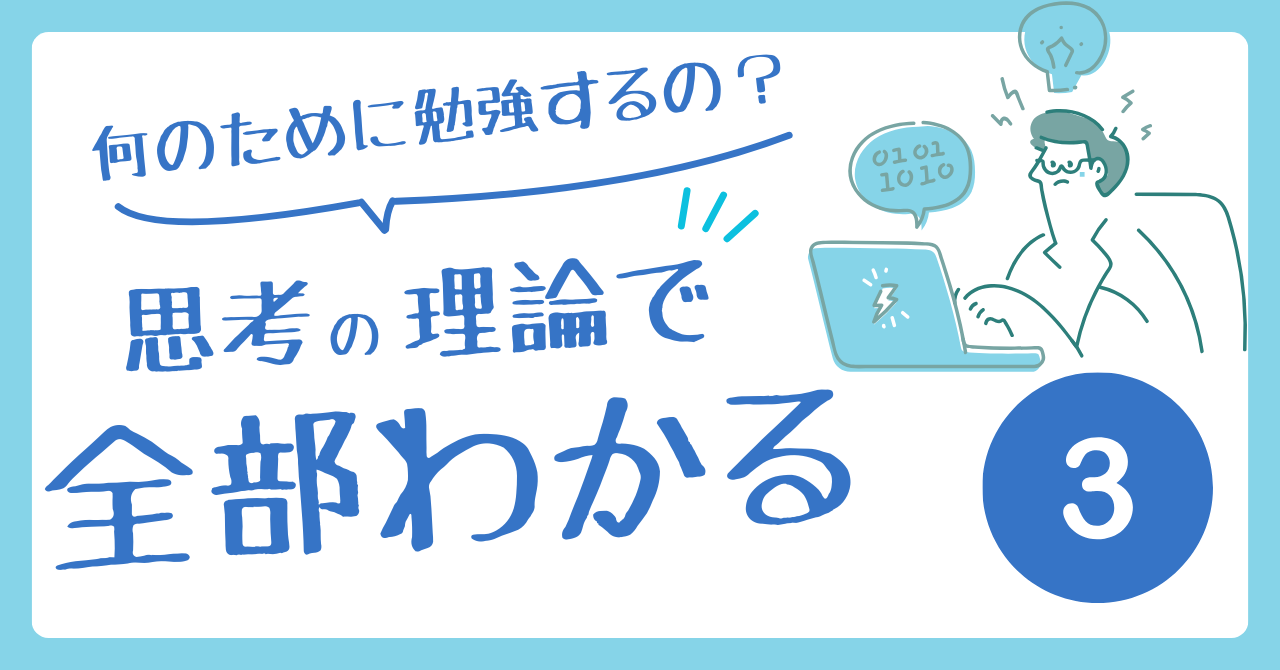
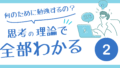
コメント